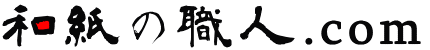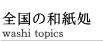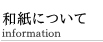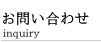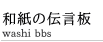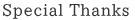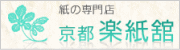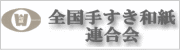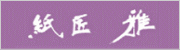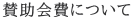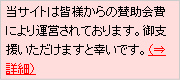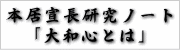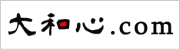京都の劇場に設置された「緞帳(どんちょう)」。
厚い布が使われるのが一般的ですが、和紙を使って光を透けさせることで、これまでとは印象の違う空間をつくり出しています。
空間を演出する和紙。薄い和紙の中に「伝統」と「挑戦」という、きらめきをすき込み、世界に評価される女性に密着しました。
光の当て方で、移ろう表情を見せるのは、銀箔(ぎんぱく)がすき込まれた和紙。バックライトを照らすと、光を透過しない銀が、影となって浮かび上がる。幻想的な和紙をすき上げたのは、堀木 エリ子さん(50)。
世界初の和紙でできた「緞帳」は、縦4メートル、幅13メートルの継ぎ目のない巨大な一枚和紙。光を透過するため、多様な演出が可能となった。
堀木さんがすき上げる和紙は、世界的なチェロ奏者、ヨーヨー・マさんの舞台も演出。クリスタルブランド「バカラ」とコラボするなど、世界からも注目を浴びている。
そんなきらめきが生み出される場所は、古都・京都にあった。桂川工房は、工房全体が大きな紙すき台となっていて、最大16メートル×6メートルの和紙を作ることができる。東京で10日から行われる展覧会に向け、ミスの許されない作業が、1カ月以上続いている。この工房で行われている作業を体験させてもらった。
すいた直後の紙に、たわしで水を打ちつけると、水滴で穴が開く。これが、堀木さん独自の手法。
堀木さんは「すき方も、自分たちの発想で考えるということが必要なわけですね。革新というのは、そういうことなんですね」と話した。
もともとは銀行員だった堀木さん。知人に誘われ、転職した会社が、たまたま和紙製品を扱っていた。
堀木さんは、その時に出会った職人のひたむきな姿に、衝撃を受けた。
堀木さんは「氷水みたいに冷たい水に手を浸して、黙々とうつむいて、原料の準備とか、紙すきをしている職人さんたちを見たんですね。なんと尊い営みなんだろうと思ったんですね」と話した。
しかし、安価な機械生産の波に押され、堀木さんの会社は閉鎖された。伝統が直面する危機を肌で感じた。
堀木さんは「誰も、なんとかしてくれる人がいなかったので、だったら自分でするしかないかと」と話した。
伝統を次世代につなぎたいと、見よう見まねで和紙をすき始めた堀木さん。しかし、そんな堀木さんの前に立ちはだかったのも、伝統だった。
堀木さんは「もう、水滴がひじから1滴、ぽたっと落ちるだけで、『損紙』と呼ばれて捨てられてしまうんですね。完璧な紙じゃないので、職人さんには」と話した。
「紙は神に通ずる」といわれるほど神聖なもの。
和紙の素人が向き合ったのは、職人たちが1500年守り続けた、真っ白で均一な和紙だった。
水をたたきつけて模様を作る手法は、ほかの職人たちから相手にしてもらえなかった。
堀木さんは「『堀木さん、そんなものね、和紙と呼ばんといて』って言われたんです。すっごく、わたし落ち込んだんですよ、その時に。職人さんが言う『伝統って、いったいなんだろう』と考えたんです。でも、伝統っていうのって、考えてみれば、1500年前には革新だったわけでしょ。それが長年愛されて、親しまれて、使われてきて、人の役に立って、今、伝統といわれているわけで。革新が育った姿が伝統なんだということに、その時、気がついたんです」と話した。
今は革新でも、継続すれば、いつか伝統となる。
そんな堀木さんの考えは、枠を超えた要望に出会うことで、形になっていった。
大きくて燃えない和紙が欲しい。卵のような骨格のない和紙が欲しい。和紙の車を作ってほしい。
堀木さんは「無知が財産だったんです。何も知らなかったんですね。だから、固定概念とか既成概念がないので、こうしたら面白いやんということが、ちゅうちょなくできたんです」と話した。
堀木さんは、紙すきの技術開発に加え、金属やガラスなど、さまざまな素材と組み合わせることで、革新を起こした。
ただ、和紙の原料である「コウゾ」だけは変わらない。
全て、堀木さんの原点である、福井県の工房から取り寄せている。
堀木さんは「(職人さんたちの仕事を守る部分もある?)そうですね」と話した。これまでの伝統と、これからの伝統、両方を追い求める日々は続く。
堀木さんは「(堀木さんにとって『きらめきJAPAN』とは?)前例がないことへの挑戦ですかね。今までやってませんから、できません。伝統というのは、こういう作り方で、こういうものだからできませんって言い出すと、それはもう、そこから前には進めないです。その前例がないことを、きちっと挑戦して、成し遂げることが、未来の伝統産業への道なんですね」と話した。
堀木さんがやって来たのは、大阪にある一般住宅。
これまでに開発した和紙の手法を、一般家庭の暮らしの中に定着させることが、今後の目標。
表情豊かな陰影を生み出す、堀木さんの和紙。
その向こうに透けて見えるのは、「未来の伝統」という名のきらめきJAPAN。 (05/03 00:40)
※堀木エリ子さんの紹介記事。テレビでも特集で放送されたようです。和紙が紹介されたことが嬉しい部分もあるのですが、それにしても伝統工芸を7分ほどの特集でフジテレビが放送するようになったことがもっとと驚き(笑)時代変わりましたねー。